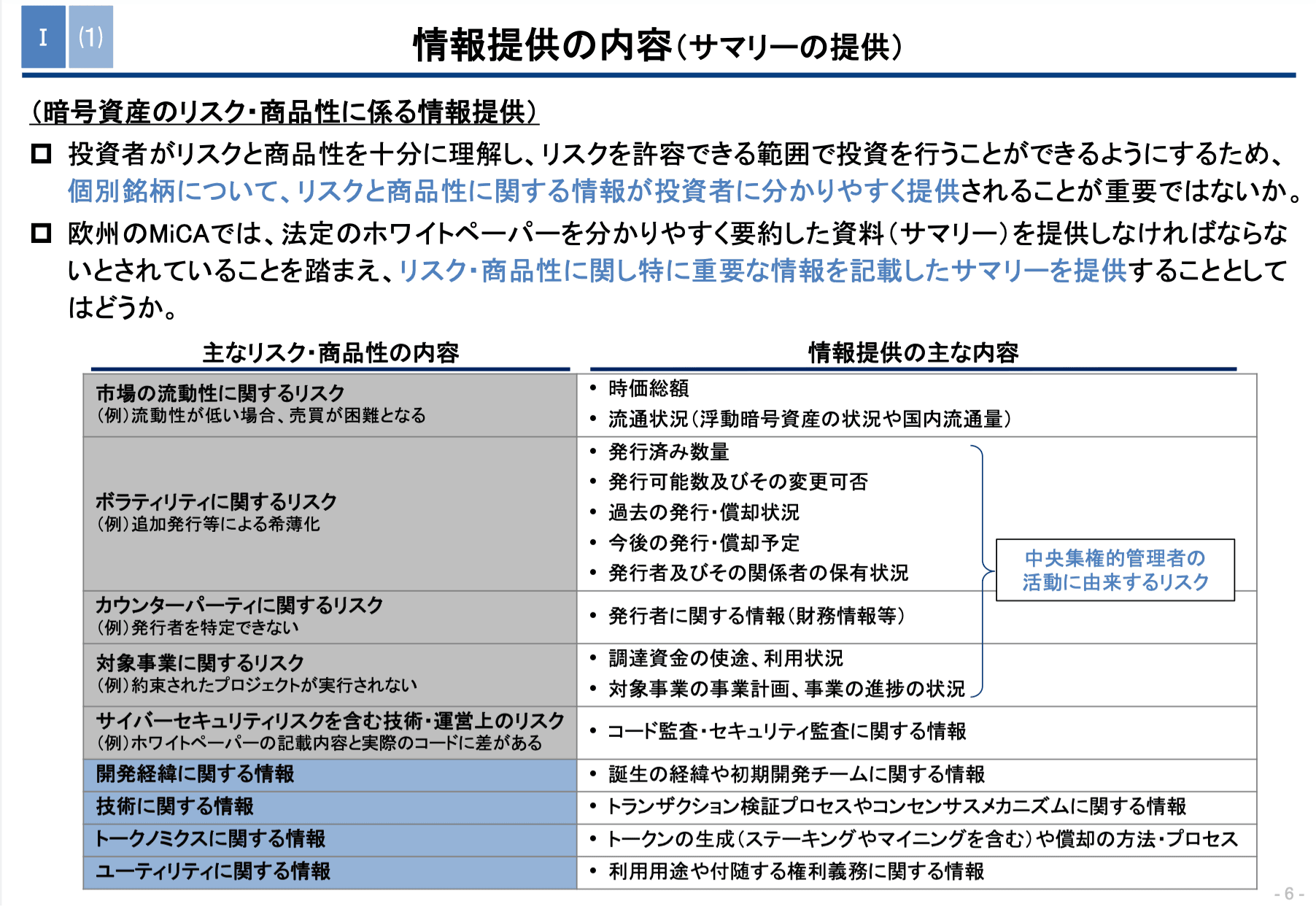
金融庁が暗号資産の管理システムを提供する事業者に対し、事前届出制の導入を検討していることが分かった。日本経済新聞によると、7日に開かれた金融審議会の作業部会で議題として取り上げられ、多くの委員が賛同した。市場では、今回の制度導入が規制の空白を埋める動きになるとの見方が強い。
現行法では国内で暗号資産交換業を営む場合、資金決済法に基づく金融庁への登録が必要となる。一方、交換業者が外部に資産管理を委託するケースは監督の対象外だった。金融庁は近く報告書をまとめ、2026年の通常国会に金融商品取引法の改正案を提出する方針だ。
日本の市場全体は投資を促しつつ、内部者取引の防止と投資家保護を進める方向にある。事業者への監督は強化されるが、税制面では環境整備を図る動きも出ている。
金融庁は7月に暗号資産ワーキンググループの初会合を開催し、暗号資産を資金決済法から金融商品取引法の枠組みに移す検討を始めた。8月には最大55%だった暗号資産の課税を、上場株式と同じ申告分離課税20%に引き下げる方針を示した。
市場関係者の間では、暗号資産が他の金融商品と同じ規制下に置かれることでETFなど新商品の開発が進み、機関投資家の参入が容易になるとの期待が広がっている。金融庁も現物ETFについて「海外動向を踏まえ、日本でも暗号資産ETFの創設を検討する」と明言した。
9月の金融審議会では、インサイダー取引の規制強化や分散型金融(DeFi)の監督基準について海外事例を参考に議論が行われた。背景には、2024年5月に発生したDMMビットコインの不正流出事件がある。警視庁と米連邦捜査局(FBI)は同年12月、この事件が北朝鮮のハッカー集団によるものだったと発表した。DMMは資産管理に日本企業 Ginco Inc. のソフトウェア「Ginco Enterprise Wallet」を使用していたことから、責任の所在を巡る議論が起きた。
Ginco Inc. はウォレットの設計ミスやバグが原因ではなく、自社は資産や秘密鍵を直接扱っていなかったと説明。不正送金もGincoから発信されたものではなく、高度なソーシャルエンジニアリングやインフラ侵害により、DMM側の操作に不正データが挿入されたと明らかにした。
日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の最新統計によると、2025年8月時点の国内現物取引額は約2兆70億円、証拠金取引額は約1兆1,739億円に達した。登録交換業者は31社と前年より増加した。
業界関係者は「日本の暗号資産市場は価格回復の段階を超え、制度整備とリスク管理が進む成長期に入った」と話す。「金融庁が管理システム事業者への届出制を検討するのも、市場拡大に対応した動きだ」と述べた。

コメント