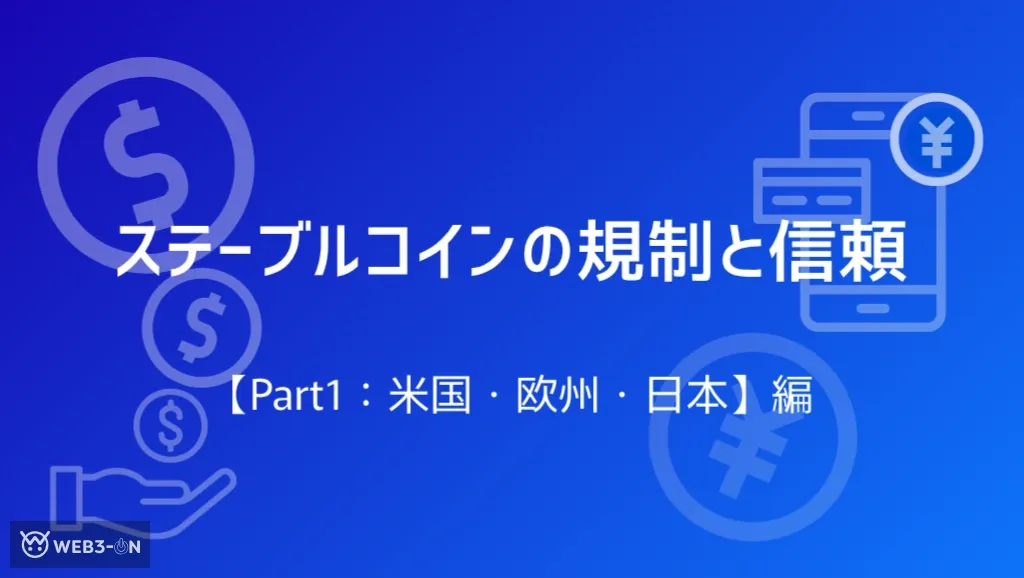
ステーブルコインは、価格の安定性とブロックチェーン技術の利便性をあわせ持つ新しいデジタル通貨として国際的に注目を集めています。とはいえ、その急速な拡大は、金融システムの安定や利用者保護という観点から各国政府に新たな課題を突き付けています。現在、世界ではステーブルコインをどのように位置づけ、どこまで規制・管理すべきかという議論が本格化しています。
この記事では、米国・欧州・日本という制度整備が先行する3地域を取り上げ、それぞれが「信頼」や「透明性」をどのように制度化しようとしているのかを比較します。
米国(US) ― 「GENIUS Act」 による制度的枠組みの確立
米国では、2025年6~7月に「Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act(通称 GENIUS Act)」が議会を通過し、ステーブルコインの包括的な法律枠組みが整備されました。その法律は、ステーブルコインの発行企業に対して、裏付け資産(米ドルや国債など)を1:1以上の比率で保有することを義務づけています。さらに、発行体や資産の保管を担う機関には、マネーロンダリング防止(AML)や経済制裁対応などのコンプライアンス体制整備が求められます。
また、利用者保護の観点から発行体が破綻した場合には、ステーブルコイン保有者が優先弁済の対象となる規定も設けられています。こうした条項は、銀行預金に準じた安全性を確保する狙いを持つものです。さらに、GENIUS ActはEUなどとの「レギュラトリー・アライメント(規制整合性)」にも言及しており、海外で発行されたステーブルコインを米国内で同扱うかという国際的な整合性にも踏み込みました。
米国の取り組みは、ステーブルコインを「発行体中心」で管理するという点で特徴的です。裏付け資産の保有と監査、利用者保護の制度化を一気に進める姿勢は評価されていますが、既存の民間発行体がどこまでこの新制度に適応できるか、また各州ごとのライセンス制度との調整をどう行うかが今後の焦点となっています。
参考:
【解説】米国「GENIUS法」まとめ|ステーブルコイン規制の新基準と日本への影響
Senate Passes Crypto-Friendly 'GENIUS Act'
欧州(EU) ― MiCA規制の実践と課題
欧州連合(EU)では、2023年採択の「MiCA(Markets in Crypto-Assets Regulation)」が、ステーブルコインを含む暗号資産市場の統一的なルールとして機能し始めています。MiCAの最大の目的は、EU域内で暗号資産サービスを提供する事業者に対して共通の基準を設け、透明性と信頼性を確保することです。ステーブルコインの発行者や仲介業者は、事前に認可を受けることが義務付けられ、定期的な報告や資産の裏付けに関する開示を行う必要があります。
2024年12月以降、MiCAは本格運用段階に入り、オランダなど一部の加盟国ではすでにライセンス認可を得た企業が登場しています。これは、EU域内でステーブルコインを合法的に発行・流通させるための新たなマイルストーンと言えます。
一方で、実務面ではMiCAと既存決済指令(例えばPSD2)との間で規制が重複するケースも見られ、企業が二重にライセンスを取得しなければならないという負担が指摘されています。また、加盟国ごとに監督機関の運用基準に差があり、「統一ルール」の実現にはまだ課題が残るのが現状です。それでも、欧州のアプローチは「厳格な枠組みの中でイノベーションを支える」というバランスを取ろうとしており、ステーブルコインをただの投機商品ではなく信頼できる決済手段として社会に定着させようとする姿勢が明確です。
MiCAの施行から約1年半が経過した2025年11月現在も、実際の適用を巡る議論は続いており、特に「国際的な相互運用性(cross-border interoperability)」が次の課題となっています。
参考:
The MiCA License: A New Era for B2B Crypto Payment Platforms - OneSafe Blog
日本(JP) ― 改正資金決済法と「実用化フェーズ」への転換
日本では、2023年に施行された改正資金決済法により、ステーブルコインが正式に「電子決済手段」として法的に定義されました。これにより、発行体・裏付け資産・監査・償還といった要素が明確に制度化され、ステーブルコイン市場の信頼基盤が整備されつつあります。
この制度の最大の特徴は「発行できる主体が限定されている」点です。銀行、資金移動業者、信託会社など、金融庁の監督下にあるライセンス保有企業のみが発行可能とされ、裏付け資産を100%保有することが義務づけられています。さらに、発行体は定期的に外部監査を受け、その残高を報告する義務があります。これにより、ユーザーは常に「1コイン=1円(または1ドル)」で換金できることが法的に保障される仕組みが整いました。
この法改正の枠組みを実際に活用した最初の事例として、JPYC株式会社が2025年8月に日本国内で初めてステーブルコイン発行ライセンスを取得し、同年10月27日に第1号となる円建てステーブルコインを発行したことが大きな話題となりました。この「JPYC」トークンは信託銀行を通じて裏付け資産を100%保管し、法定通貨と1:1での償還が保証されています。また、Progmat Coin(三菱UFJ信託銀行系)やDCJPY(DeCurret DCP主導)など、複数の国内金融機関・企業が同様の仕組みでの発行を準備しており、日本国内では「ポストCBDC」として民間主導の円デジタルマネー構想が現実味を帯びています。
さらに注目すべきは、日本の規制がブロックチェーン事業者との協調を前提に設計されている点です。たとえば、Web3やスマートコントラクト分野では、これらのステーブルコインが決済トークンとして利用可能になるよう、技術的な連携が進んでいます。日本ではステーブルコインをただの「規制対象」としてではなく、「デジタル経済の信頼基盤」として育てる方向に動き出したといえます。
参考:
金融庁「事務局説明資料 ― 電子決済手段(ステーブルコイン)に関する規制の再点検」
【国内初】日本円建ステーブルコイン発行へ-資金移動業者の登録を取得
【国内初】日本円ステーブルコイン「JPYC」および発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」を正式リリース
「信頼」を制度化する3つのアプローチ
米国・欧州・日本はそれぞれ異なるアプローチでステーブルコインの制度化を進めています。米国は発行体規制と利用者保護を法律で明確化し、欧州は統一ルールの下で市場の秩序を整えつつ実務調整を続け、日本は法的定義と実用化を並行して進めることで実地検証を進めています。
これらの共通点は、「信頼の通貨」をいかに制度的に裏づけるかという一点にあります。裏付け資産の保全、第三者による監査、そして法的な償還保証など、これらが組み合わさることで、ステーブルコインは単なる暗号資産ではなく、社会的に認められる「新しいマネー」へと進化しつつあります。
次回のPart 2(韓国・シンガポール・香港)では、アジア圏での規制の進展について、より深く掘り下げていきます。

コメント