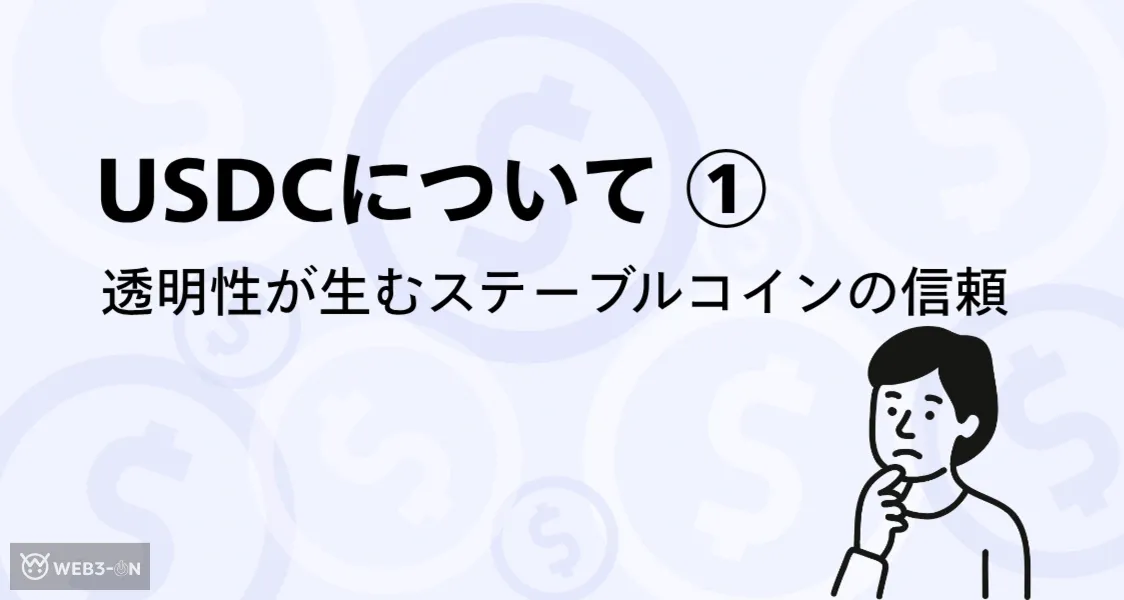
ステーブルコイン市場は、ブロックチェーンを基盤としたデジタル通貨の中でも「価格の安定」と「決済での利便性」を両立する存在として急速に拡大しています。その中でも米ドル連動型のUSDC(USD Coin)は、高い透明性と信頼性を前面に打ち出し、成長を続けるデジタル資産市場において独自の地位を確立してきました。
本記事では、USDCの発行体であるCircleの事業モデルや規制への対応、そして市場での役割と今後の課題について整理し、ステーブルコインの信頼性を支える仕組みを考察します。
USDCの誕生背景と発行体 ―「透明性の欠如」への問題意識から生まれたプロジェクト
USDCは米国企業のCircleと暗号資産取引所Coinbaseが中心となって立ち上げたプロジェクト「Centre(センター)コンソーシアム」から生まれ、2018年に発行が始まりました。Centreはガバナンスや技術仕様を定める共同体として設計され、当初はCircleとCoinbaseが共同でUSDCの発行・普及を進めていましたが、後に発行責任はCircleに一本化される方向に移行しています。
誕生の背景には、既存の主要ステーブルコイン(特にUSDT=Tether)に対する透明性や裏付け資産の懸念がありました。USDTは市場流動性で優位に立つ一方で、準備資産の構成や監査の透明性で繰り返し批判を浴び、これに対してUSDCはより厳格な裏付け・監査体制を示すことで差別化を図った経緯があります。
参考:
「USDC」発行の米サークル、売却に向けリップルおよびコインベースと協議か=報道
実現フェーズに入ったデジタル通貨~ステーブルコイン・トークン化預金の相違点・導入時の検討ポイント~
USDCの仕組みと構造 ―「1 USDC = 1 USD」を支える準備金の運用と開示
USDCは「1 USDC = 1 USD」の価値を維持するために、発行体が準備金を保有する仕組みを採っています。Circleは準備金として米ドル現金や米国短期国債などの高流動性・低リスク資産を中心に保有する方針を公表しており、その状況は定期的な報告や透明性レポートで開示されています。
準備金の検証については、外部会計事務所による月次の確認が行われており、Circleはこうした報告書を公開することで、準備金の健全性に関する説明責任を果たしています。具体的には、準備金の内訳(現金、短期国債、コマーシャルペーパー等)や総額と発行済みUSDCの比率が開示されます。ただし「監査」と「確認」は法的な厳格さで差があるため、実務上は第三者の信頼できる定期報告の有無が市場の信頼を左右します。
加えて、Circleはグローバルにカストディ(準備金保管)や運用を分散させることで、一箇所の金融機関リスクに依存しない体制をとることを明示しています。この分散管理により、銀行破綻や資金凍結といった単一点リスクの低減が図られています。
参考:Transparency & Stability - Circle
規制対応と信頼の獲得 ― 法整備がUSDCモデルと親和する理由
USDCの成長と信頼獲得は技術的仕組みだけでなく、規制対応の積み重ねに負うところが大きいです。米国では近年ステーブルコイン規制が急速に整備され、2025年に成立したとされるGENIUS Act(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)などの動きは、発行体に対して高品質流動資産での裏付け・資金分別・月次の証明・AML(マネーロンダリング対策)遵守を求める点でUSDCの事業モデルと親和性が高く、結果的にUSDCの法的な位置づけと業務基盤の安定化に寄与しています。
Circleは各地域でのライセンス取得や現地法人の設立を進めており、例えば、Circle SingaporeやCircle Japanといった地域法人を通じて、現地ルールに沿った提供体制を構築しており、これが国際展開とローカル規制遵守の両立につながっています。さらに、透明性の観点では、CircleはTransparency Report(準備金の公開)や外部による確認作業を継続して公表することで、発行体としての説明責任を果たしている点が評価されています。ただし、規制の細部(どの資産を許容するか、資産運用で得た利回りの扱いなど)は地域ごとに差があり、これが国際展開の課題となっている点は注意が必要です。
参考:
Stablecoins: Issues for regulators as they implement GENIUS Act
Circle Expands USDC Access in Japan
市場での立ち位置と課題 ― 監査・国際規制・CBDCとの共存がカギ
市場ではUSDCは「透明性を重視する」勢力の代表と見なされており、取引所での流通や機関投資家の利用においてはUSDT(Tether)との差別化が進んでいます。実際、USDTは市場シェアで上回る場面が多いものの、その準備資産の一部にリスク資産が含まれる点が批判されてきました。一方でUSDCは保守的な準備資産構成と公開報告により、金融機関や規制当局に受け入れられやすい立ち位置を築いています。
とはいえ、課題も依然として残されています。1つ目は、準備金の「完全性」と「実証(第三者監査)」の双方をどのように制度的に担保するかが、引き続き注目されています。2つ目は、GENIUS Actのような厳格化はUSDCに追い風となる一方で、利回り提供(rewards)や取引所との収益配分など、商業モデルと規制の調整が必要です。(規制が商業モデルを制約する可能性)
3つ目は、国際展開の障壁です。各国で許容される準備資産の範囲、AML/KYC基準、税処理、そしてMiCAなど地域法令との整合性が求められ、これらを満たしつつスピード感を持って事業を展開するのは容易ではありません。4つ目の課題として、CBDC(中央銀行デジタル通貨)との共存も検討課題です。CBDCは国家発行のデジタル通貨であり、ステーブルコインとは異なる政策目的を持つため、将来的な役割分担や相互運用性をどう設計するかが問われます。
参考:
USD Coin vs. Tether Statistics 2025: Market Trends, Compliance • CoinLaw
The Loophole Turning Stablecoins Into a Trillion-Dollar Fight | WIRED
「信頼されるデジタルドル」への道をどう築くか
USDCは、しっかりとした準備金の管理と高い透明性を保つことで、ステーブルコインへの信頼を高めてきました。アメリカを中心に進む規制の整備もUSDCの仕組みとよく合っており、今後は金融のインフラとしてさらに重要な役割を担う可能性があります。その一方で、第三者による本格的な監査の仕組みづくりや、国ごとのルールとのすり合わせ、CBDC(中央銀行デジタル通貨)との共存など、まだ解決すべき課題も残っています。世界中で安心して使える「デジタルドル」を実現するためには、技術・法律・運営のバランスをとりながら進化していくことが大切です。

コメント