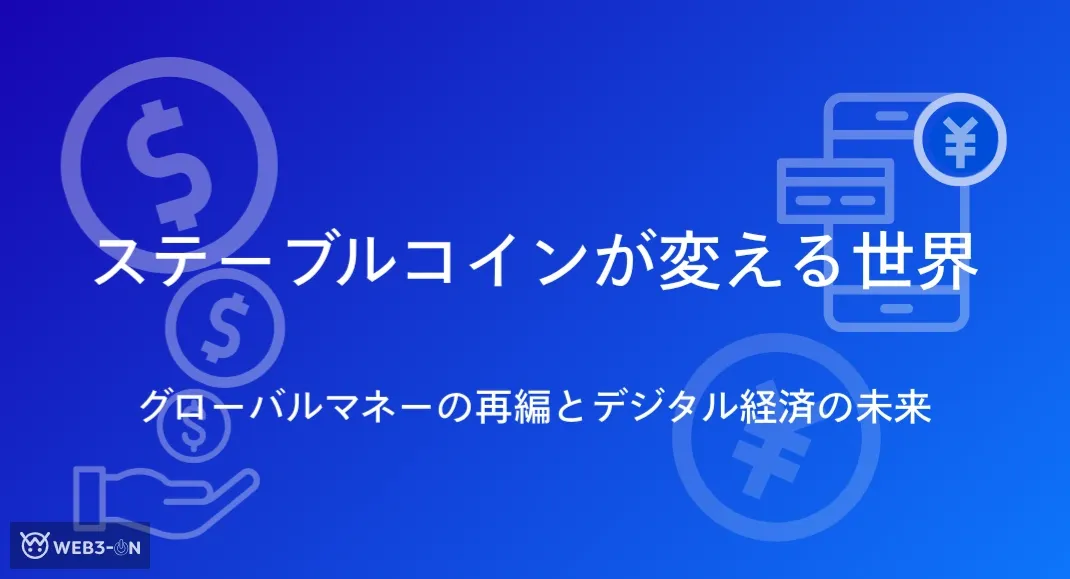
ブロックチェーンの世界は今、ステーブルコインが静かに、しかし確実に存在感を高めています。ステーブルコインとは、法定通貨に価値を連動させた暗号資産の一種で、価格変動が少ないのが特徴です。この「安定したデジタルマネー」が、国際決済や金融の仕組みそのものを変えようとしています。
この記事では、ドルを中心とした国際通貨体制との関係、Web3やリアル資産のトークン化(RWA)などでの活用、企業や政府による制度化の動き、そして国家通貨と民間デジタルマネーが共存する未来像に焦点を当てながら、ステーブルコインが描く新しいお金の姿を追っていきます。
ステーブルコインはドルの力を強めるのか、それとも揺るがすのか
現在発行されているステーブルコインの役9割は米ドルに連動しています。つまり、ブロックチェーンの世界でも「ドル経済圏」が広がっているのです。
一方で、これはドルの影響力をさらに強める動きと見る人もいれば、各国の通貨主権を脅かすリスクと考える人もいます。特に、インフレや為替不安のある新興国では、地元通貨よりもステーブルコインを使う方が安心だという声も増えています。デジタル空間の中で、ドルの存在感はこれまで以上に強まっていると言えるでしょう。
広がるステーブルコインの活躍 ― Web3、RWA、ゲームなど
ステーブルコインの使い道は、もはや投資だけにとどまりません。Web3決済では、NFTの売買やDeFiサービスでの送金に活用されています。さらに注目されているのがRWA(リアルワールドアセット:現実資産のトークン化)の分野です。例えば、シンガポールのUBSやトークン化企業Sygnumは、不動産や国債などの実物資産をブロックチェーン上でトークン化し、その配当や利息の支払いをUSDCなどのステーブルコインで行う実証を進めています。また、MakerDAOも米国債などの実物資産を担保にしたステーブルコイン運用を行っており、RWA市場は既に数十億ドル規模に拡大しています。これにより、国境を越えた投資や資産運用がよりスムーズに行えるようになっています。
参考:UBS, PostFinance and Sygnum Conduct Cross-Bank Payments on Ethereum
ゲーム業界でも、ステーブルコインは新しい経済圏を生み出しています。Sky Mavis(Axie Infinity)やGala GamesなどのPlay-to-Earn(遊んで稼ぐ)型ゲームでは、報酬や取引の決済にステーブルコインを採用する動きが進んでいます。トークン価格の変動に左右されずに補修を受け取れる仕組みが整い、プレイヤーが安心して参加できる環境が生まれています。
参考:Coins to watch in 2022: To Infinity and Beyond - Axie Infinity rules the Play-2-earn space
民間企業と政府の協業事例 ― Visa、PayPal、JPYC、Circle・Tether
ステーブルコインをめぐる動きは、グローバル企業から日本のスタートアップまで、決済や送金の新しいインフラを築こうとする動きが広がっています。その先には、民間と政府が協調してつくる次世代の通貨エコシステムが見え始めています。
Visa ― ステーブルコイン決済の本格導入へ
Visaはここ数年、ブロックチェーンを活用した決済技術に力を入れています。2025年には、USDC(米ドル連動型ステーブルコイン)を自社の決済ネットワークに正式導入し、EthereumやSolanaなど複数のブロックチェーンを跨ぐ清算を実現しました。これにより、従来の国際送金よりも高速かつ低コストでの決済が可能になっています。
Visaの幹部は「ブロックチェーンはカードネットワークの延長線上にある次世代の決済基盤」と語っており、今後はステーブルコインを国際決済の標準インフラとして位置付けていく構えです。
参考:Visa - Visa Expands Stablecoin Settlement Support
PayPal ― 「PYUSD」でデジタルドル決済を推進
2023年、PayPalは自社ブランドの米ドル連動型ステーブルコイン「PYUSD」を発表しました。このコインは米ドル預金と短期国債で100%裏付けされており、常に1:1で米ドルに換金できます。2025年には、ブロックチェーンを活用した国際送金や小口決済にも活用が広がり、既存のPayPalアカウント間での送金にも対応しています。さらに、決済インフラ大手Fiservとの提携を通じて、商業決済ネットワークでの活用も進んでいます。こうした取り組みにより、ステーブルコインが「実際に使えるデジタルドル」として日常の決済の中に浸透し始めています。
参考:
Press Release: PayPal Launches U.S. Dollar Stablecoin - Aug 7, 2023
PayPal Drives Crypto Payments into the Mainstream, Reducing Costs and Expanding Global Commerce
JPYC ― 日本発の円建てステーブルコイン
日本でもステーブルコインの実用化に向けたチャレンジが進んでおり、その代表格がJPYC株式会社です。同社は日本円と1:1で連動する円建てステーブルコイン「JPYC」を発行し、2025年10月には本格的に市場へ投入されました。JPYCは、円の信頼性とブロックチェーンの利便性を両立させるモデルとして注目されており、既にクレジットカードの返済手段としての導入が発表されています。その流れの中で同社は「デジタル円」の民間版としてのポジションを狙っており、政府の資金決済法改正や関連制度整備が王位風邪となっています。
参考:
【国内初(※1)】クレジットカード返済方法に、日本円建ステーブルコイン「JPYC」が導入されます。
Circle・Tether ― 世界のステーブルコイン市場を支える二大軸
米Circle Internet Group社は、USDCの発行体として、金融機関や政府との連携を広げています。特にVisaとの提携を通じて、企業間取引(B2B)や国際清算におけるUSDCの利用が進んでおり、既存の決済ネットワークにステーブルコインを統合する動きが加速しています。2025年には、MastercardやFIS(金融サービスソリューション企業)との提携も発表され、銀行や加盟店がUSDCを使ってグローバル決済や清算を行える仕組みが整っています。
参考:
Stablecoin Giant Circle Is Launching a New Payments and Remittance Network
一方で、Tether(USDT)は現在、世界最大の流通量を誇るドル連動ステーブルコインです。2025年時点で発行総額は1,200億ドルを超え、USDCを上回る規模となっています。USDTは取引所やDeFi、国際送金などで最も広く利用されており、特に中南米や東南アジアでは、インフレ回避やドル代替として生活レベルで使われ始めています。Tether社は裏付け資産の透明性を高めるため、監査報告書を四半期ごとに公開し、規制対応にも注力しています。
こうした民間の動きに合わせて、各国政府も制度整備を加速しています。シンガポール、香港、韓国、日本では、ステーブルコインの裏付け資産・償還義務・ライセンス制度などを定めた法制度が順次整備されつつあります。政府の関心は、規制というよりも安全で信頼できるステーブルコイン市場を構築することへと移行しています。
新しい通貨インフラとしてのステーブルコイン
ステーブルコインの魅力は、誰もがアクセスできる開かれた金融システムを実現できる点にあります。銀行口座を持たない人でも、スマートフォン一つでデジタルマネーを利用できることがこの仕組みの最大の強みです。
また、ブロックチェーン技術によって国境や通貨の壁を越えて資金を送金できる新しいマネーインフラが実現のものとなっています。各国では、中央銀行が発行するデジタル通貨(CBDC)と、民間企業が発行するステーブルコインの役割分担を意識した制度設計が進められており、公的通貨の安定性と民間のイノベーションを両立させる取り組みが進む中で、次世代の決済インフラとしての形が徐々に整ってきています。
変わりゆく通貨の形 ― デジタルマネーがもたらす次の時代へ
ステーブルコインは、「投資や投機の対象」から「実際に使える通貨」へと進化しています。国が発行する通貨と、民間が生み出すデジタルマネーが共に流通し、世界中の人々が瞬時に価値をやり取りできる環境が整いつつあります。こうした動きは、単なる技術革新ではなく、私たちがお金の使い方や価値のあり方を見つめ直すきっかけにもなっています。各国がCBDCの整備を進め、民間がステーブルコインを発行することで、「国家通貨と民間デジタルマネーが共存する新しい通貨体制」が少しずつ形になり始めています。
ステーブルコインは、グローバル経済の仕組みそのものを静かに、しかし確実に変えています。それは、お金の概念そのものが国境を越えて再定義される時代の幕開けと言えるでしょう。

コメント